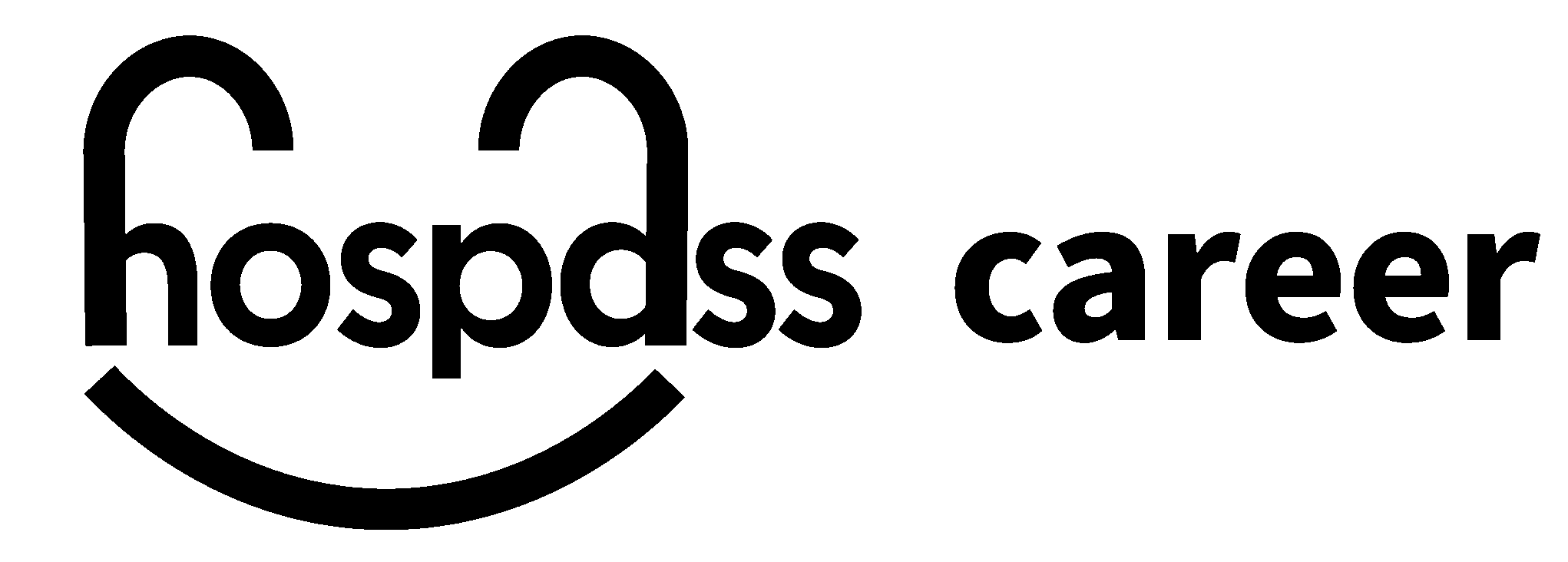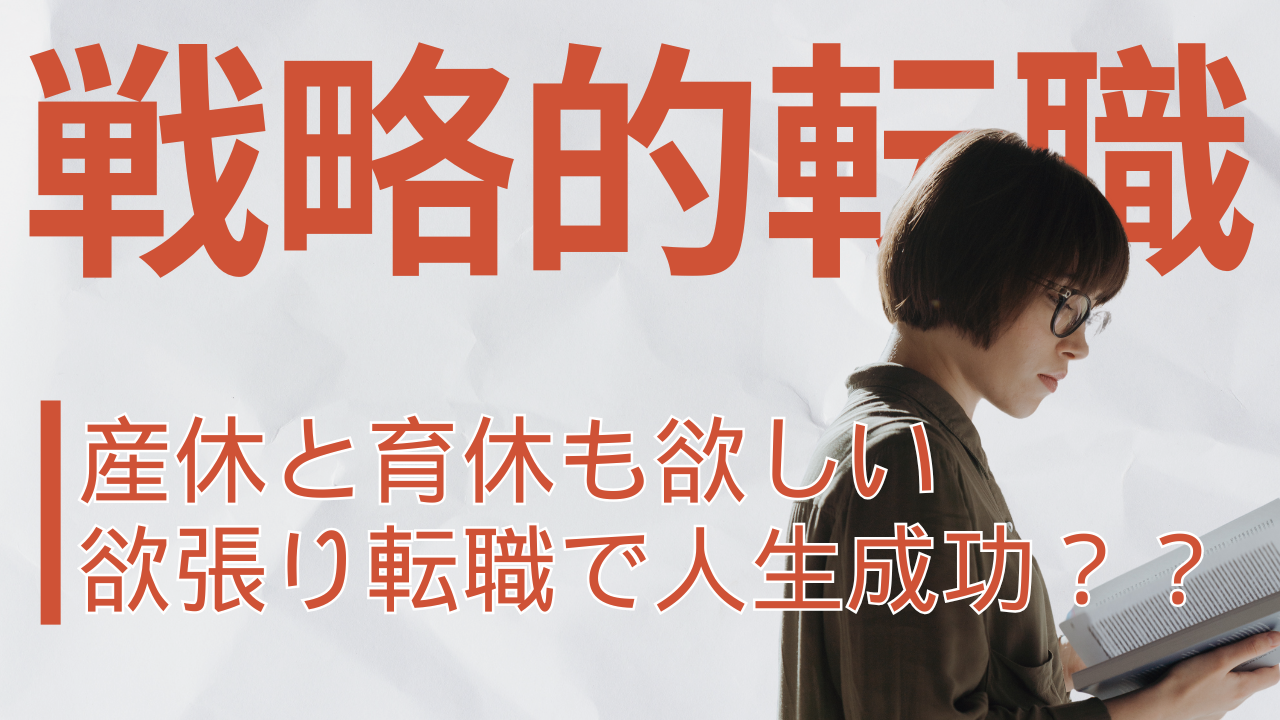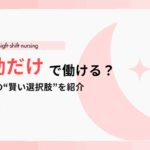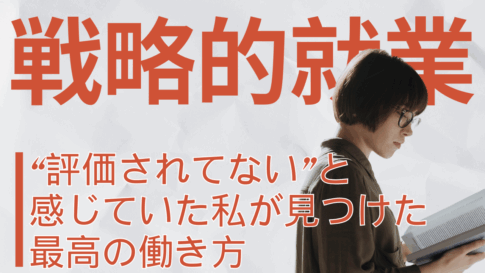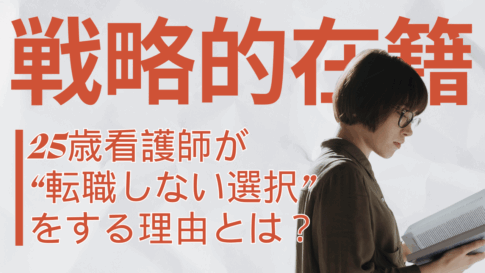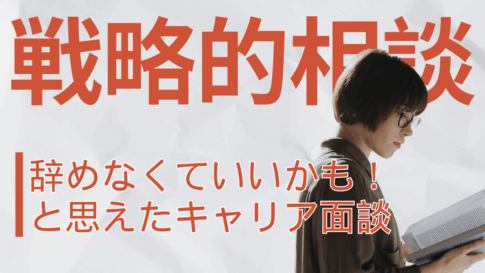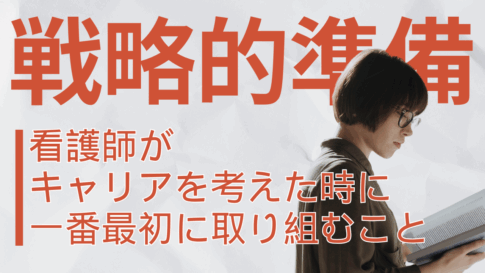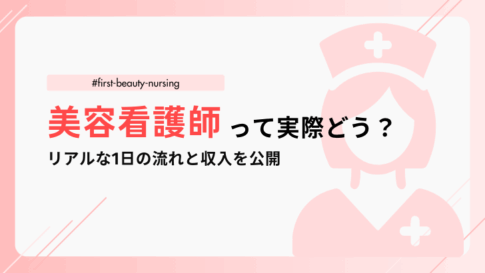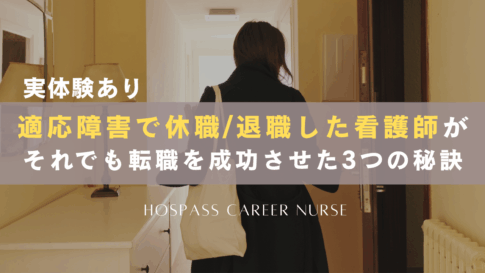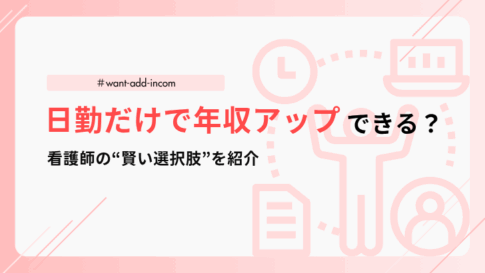「いずれ結婚や出産もしたい。でも今の職場のままでいいのかな?」そんな不安を抱えながら働く看護師は少なくありません。
病棟勤務のハードな環境では、将来を考えるほど心も体も追いつかないことも。だからこそ、“制度が使える職場”への転職は、人生設計の一部として考える価値があります。
本記事では、産休・育休制度の基本から、キャリアを止めずに未来を描くための転職タイミングまで、わかりやすく整理します。
結婚・出産と看護師のキャリア、どう向き合う?
結婚や出産といったライフイベントを意識し始めたとき、看護師としての働き方に不安を抱える人は少なくありません。
夜勤や不規則な勤務が当たり前の病棟勤務は、心身への負担も大きく、これからの人生をどう設計していくべきか迷う瞬間が訪れます。ここでは、ライフイベントとキャリアの両立に向き合うためのヒントを整理します。
夜勤や不規則な勤務がもたらす心身の負担
病棟勤務の看護師にとって、夜勤は避けて通れない業務のひとつ。けれど、生活リズムが乱れることで生理不順や慢性的な疲労感を抱えたり、プライベートとの両立が難しくなったりするケースもあります。
特に年齢を重ねるごとに、心と身体の変化を自覚しやすくなり、「この働き方を続けていけるのか」という疑問が芽生えるようになります。
結婚・妊娠でキャリアが中断する不安
結婚を機に職場を変えたり、妊娠で体調が変わったりすることで、キャリアが一時的に止まってしまうのではないかという不安を抱える看護師は多くいます。
「今の職場は産休・育休が取りづらい」「戻れる保証がない」と感じている場合は、制度面の不備や職場文化がその原因であることも少なくありません。
実際、制度が整っている職場であれば、妊娠中のサポートや産休明けの復職もしやすくなります。
まずは“選択肢があること”を知ることから
キャリアと家庭を天秤にかける必要はありません。今は、日勤のみの働き方、フレックス制度のある職場、産休・育休取得実績が豊富なクリニックなど、選べる環境が広がっています。
まずは「看護師でも両立できる働き方がある」という事実を知ることが、行動の第一歩。知ることで、未来への不安が「備え」に変わっていきます。
知っておきたい「産休・育休制度」の基本
結婚や出産を見据えて働き方を考える際、必ず押さえておきたいのが「産休」「育休」に関する制度です。
医療現場では日々忙しく働く中で、制度について詳しく調べる余裕がない人も多く、「なんとなく聞いたことがあるけれど、自分に当てはまるのかよくわからない」という声も少なくありません。
このセクションでは、産前産後休業・育児休業の違いや、休業中に受けられる給付金、健康保険・年金の扱いについて整理します。
産前産後休業と育児休業の違い
「産休」「育休」とひとくくりに呼ばれることが多いものの、制度としては別物です。
まず「産前産後休業(産休)」は、労働基準法で定められている制度で、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から出産後8週間の間、就労を免除できる期間のことを指します。
この期間は、原則として本人の申出により取得が可能で、出産後8週間以内は医師の許可がなければ就労できません。
一方、「育児休業(育休)」は、男女問わず子どもが1歳(条件を満たせば最長2歳)になるまで取得できる制度で、雇用保険に加入している人が対象です。育休は、母体の回復ではなく「子育てを行うため」の制度である点が、産休との大きな違いです。
また、産休が法律で義務付けられているのに対し、育休は原則として本人の申請によって取得が決まるため、申請のタイミングや手続きも重要です。
産前産後休業(産休)とは?
- 出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)〜出産後8週間の期間
- 労働基準法で定められた「休業できる権利」
- 出産後8週間は原則として働けない(医師の許可があれば可)
育児休業(育休)とは?
- 子どもが1歳(条件により最長2歳)になるまで取得できる制度
- 男女とも取得可能
- 本人の申請が必要(義務ではない)
育休中に支給される「育児休業給付金」とは
育休中の最大の懸念は「収入がなくなること」ですが、実際には雇用保険に基づく「育児休業給付金」が支給されます。これは、育休開始から6か月間は原則として月給の67%、その後は50%が支給される仕組みです(上限あり)。
たとえば月収30万円の看護師であれば、最初の6か月は約20万円、以降は15万円程度の給付が見込まれます。
さらに、この期間中は「非課税」であるため、実質的な手取りで見れば通常勤務時の7〜8割近くに相当するケースもあります。また、保育園に入れなかったなどの事情がある場合は、条件を満たせば1歳以降の延長も可能です。
加えて、産休中にも健康保険から「出産手当金」が支給されるため、無収入になるわけではありません。
育児休業給付金とは?
- 雇用保険に加入していれば誰でも対象
- 支給額の目安
- 育休開始〜6か月:賃金の67%
- 7か月目以降:賃金の50%
- 非課税のため、実質的な手取りは7〜8割程度
給付金の例(※月収30万円の場合)
- 最初の6か月:約20万円/月
- それ以降:約15万円/月
その他に受け取れるお金
- 「出産手当金」…産休中にも健康保険から支給される
- 「出産育児一時金」…出産時に42万円が支給される(加入保険による)
【参考①】育児休業給付金についての詳細は厚労省公式ページも参照https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
【参考②】育児休業給付金の詳細は厚生労働省「育児休業給付金のご案内」参照https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
健康保険・年金の取り扱いと“空白期間”のリスク
育休中は、会社に出勤していなくても「健康保険」や「厚生年金保険」に加入し続けることができ、その保険料は免除されます。つまり、将来の年金受給額に影響を与えることなく、社会保険上の資格を維持できるということです。
これは、長期的なキャリア形成において大きなメリットです。
ただし、注意したいのは「空白期間」の発生です。たとえば、契約社員や非常勤などで「雇用保険に加入していない」「社会保険の対象外」である場合、育休取得の条件を満たさないことがあります。
また、退職後に出産を迎えるとこれらの制度が使えない可能性があるため、転職や雇用形態の変更を考えている場合は、制度を活用できるタイミングを慎重に見極めることが重要です。
健康保険・厚生年金の扱い
- 育休中は会社が申請すれば、保険料は全額免除
- 免除期間中も「加入期間」として扱われる=将来の年金額に影響なし
- 医療費の自己負担や扶養の扱いもそのまま
注意したい「空白期間」
- 以下のような場合、制度が使えない/不利になることもあります
- 雇用保険未加入(非常勤・契約など)
- 産休・育休取得前に退職した場合
- 転職直後で「加入期間」が足りない場合
対策としては…
- 転職を考えるなら「入職から1年以上在籍」の職場を選ぶ
- 「社会保険完備」「産休育休取得実績あり」の職場か確認
出産や育児に関する制度は、知っているかどうかで大きく人生の安心度が変わります。「制度を使いこなす」ことは、賢くキャリアを築いていくための第一歩です。
次のセクションでは、こうした制度が実際に活かせる職場をどう選ぶか、その視点について深掘りしていきます。キャリアと出産を両立させるうえで「転職のタイミング」は重要な検討ポイントです。
転職のベストタイミングは“妊娠前”?“出産後”?
理想の働き方を叶えるには、制度の利用条件やライフイベントの計画を見据えて、戦略的に時期を選ぶことが欠かせません。ここでは、「妊娠前・出産後・制度利用後」の3つの観点から、それぞれのメリットと注意点を整理します。
妊娠前の転職が有利な理由
もっともおすすめされるのは、「妊娠前に転職を済ませておくこと」です。その理由は以下のとおりです。
- 雇用保険や社会保険の加入条件を満たしやすい
→育児休業給付金や出産手当金など、各種手当の支給対象になるには、転職先で一定期間働く必要があります(雇用保険:1年以上が目安)。 - 職場環境や人間関係に慣れておける
→妊娠初期の体調変化にも、信頼関係がある職場のほうが配慮してもらいやすい。 - 「育休実績」や「時短制度」があるか確認できる
→事前に、制度の整備状況や取得実績を面接時に確認することも可能です。
【参考③】育休給付金や出産手当金の支給要件には、「雇用保険への加入」「継続勤務期間」などが条件とされています。厚労省:https://www.mhlw.go.jp/
産後の転職が“リスタート”に向くケース
出産後の転職も、決してネガティブな選択肢ではありません。むしろ、以下のようなケースでは「再スタート」として前向きに捉えられます。
- 育児に合った働き方を選びたいとき
→日勤のみ・時短勤務・自宅からのアクセスが良い職場など、育児との両立がしやすい職場に絞って選べる。 - ライフステージに合ったキャリアに軌道修正したいとき
→訪問看護やクリニック勤務など、「夜勤がない」「急変が少ない」環境にシフトする人も多くいます。 - 転職をポジティブに説明できる
→「家庭とのバランスを大事にしたい」「新たな働き方を模索している」といった前向きな理由が受け入れられやすい傾向もあります。
在職中に制度を“利用してから”転職する選択も
中には、「今の職場で産休・育休を取得してから、復職後に転職する」というパターンを選ぶ方もいます。この選択肢には以下のような特徴があります。
- 制度を活用して安心して出産・育児ができる
→「産休・育休制度」が整っている職場であれば、安定した収入を確保しながら育児に専念できます。 - 復職後に「やっぱり違う」と気づいたら転職でも遅くない
→焦って決めるよりも、子どもの成長や家族の状況を見ながら判断できるメリットがあります。
ただし、復職後すぐの退職は職場への影響も大きくなるため、感謝と誠意を持って退職の意向を伝える姿勢が大切です。
「制度が使える職場」と「使いにくい職場」の違い
「産休・育休制度はある」と書かれていても、実際に使いやすい職場とそうでない職場には大きな差があります。制度が形だけのものになっていないか、現場の空気感まで含めて見極めることが、安心して働き続けられるかどうかのカギを握ります。
ここでは、制度の“使いやすさ”を見極めるポイントを整理してお伝えします。
「制度はあるのに誰も使っていない」職場のリアル
実は多くの職場に制度自体は整備されています。
しかし、いざ申請しようとすると「前例がない」「人手が足りないから戻ってきてほしい」とプレッシャーをかけられるケースも少なくありません。
- 就業規則には載っているが、実際に使われたことがない
- 使ったことで評価が下がるような“空気”がある
- 上司や同僚の理解がなく、申請しにくい
このような「制度が使いにくい職場」では、取得後の復帰もしづらく、結果的に退職を選ぶ人も多いのが実情です。
先輩ママ看護師がいる職場は心強い
一方で、制度を実際に使ってきた先輩がいる職場では、理解や支援体制が整っていることが多くあります。
- 産休・育休を取得した看護師が複数いる
- 復帰後も時短勤務や日勤専従など、柔軟に働いている
- 子育てと両立しているロールモデルが身近にいる
こうした環境では、「自分も制度を利用していいんだ」という安心感があり、不安なくキャリアを築いていける土壌があります。
面接時に聞いておくべき「産休・育休」質問集
転職活動中の面接では、以下のような質問をさりげなく投げかけておくことで、職場の“本音”を探ることができます。
- 「育休から復職された方は今どれくらい働いていますか?」
- 「時短勤務の方の割合はどれくらいですか?」
- 「ライフステージに応じた働き方の調整は可能ですか?」
- 「実際に産休・育休を取った方がどれくらいいらっしゃいますか?」
ポイントは“制度の有無”ではなく、“実績と柔軟性”に注目すること。質問の反応や回答の具体性を見れば、制度が使いやすい職場かどうかが見えてきます。
「私らしいキャリア」のためにできること
結婚、妊娠、出産──ライフステージが変わるとき、看護師としての働き方にも迷いが生まれるものです。「この先どうなるんだろう」「仕事を続けられるかな」と不安になるのは当然のこと。
でも、その不安をただ抱え込むのではなく、“自分らしいキャリア”を築くための第一歩として捉えることができます。
転職は“保険”ではなく“戦略”で考える
多くの人が、職場に不安を感じたときに「辞めた方がいいのかな…」と漠然と考えます。でも本来、転職は“逃げ”や“保険”ではなく、ライフプランに沿った戦略的な選択として活用できるものです。
- 将来の出産を見据えて、日勤中心の職場に切り替える
- 育休制度が整っている職場へ事前に移っておく
- ワークライフバランスを整えた上で、長期的なキャリアを設計する
今の自分と未来の自分、どちらにも目を向けた判断が大切です。
「まずは話してみる」ことで見えてくる道もある
自分一人で考えていても、選択肢が狭まってしまうことがあります。だからこそ、「まずは話してみる」ことが大切。相談することで初めて、「そんな働き方もあるんだ」と気づけることがあります。
- 「転職するかどうか迷っている段階でも相談できる場所」
- 「ライフプランに合わせてアドバイスをくれる人」
- 「同じ悩みを経験した先輩のリアルな声」
こうした対話から、“私らしいキャリア”のヒントが見えてきます。
将来に備えるための転職は、今の自分にとっても、未来の自分にとっても、大きな価値のある選択です。「何かをあきらめる転職」ではなく、「未来を広げる転職」を。選ぶのは、あなた自身です。
「人生の変化」と向き合うことで、キャリアの選択肢は広がる
看護師という仕事は、社会的にも専門性が高く、多くの人に必要とされています。
しかし、結婚や出産といったライフイベントと向き合うタイミングでは、「このまま働き続けられるのか」「キャリアを中断しないためにはどうすればいいのか」と悩む人も多いでしょう。
大切なのは、“制度を知ること”と“環境を選ぶこと”。産休・育休をしっかり活用できる職場があること、妊娠前後の転職が不利にならない道があることを知れば、未来の不安も少しずつやわらぎます。
キャリアは「積み上げるもの」であり、「守るもの」でもあります。今の環境に不安があるなら、まずは情報を集めて、小さく動いてみることから始めてみませんか?LINEでは、制度や転職に関する個別相談も受け付けています。
あなたにとっての“ちょうどいい未来”を、一緒に見つけていきましょう。