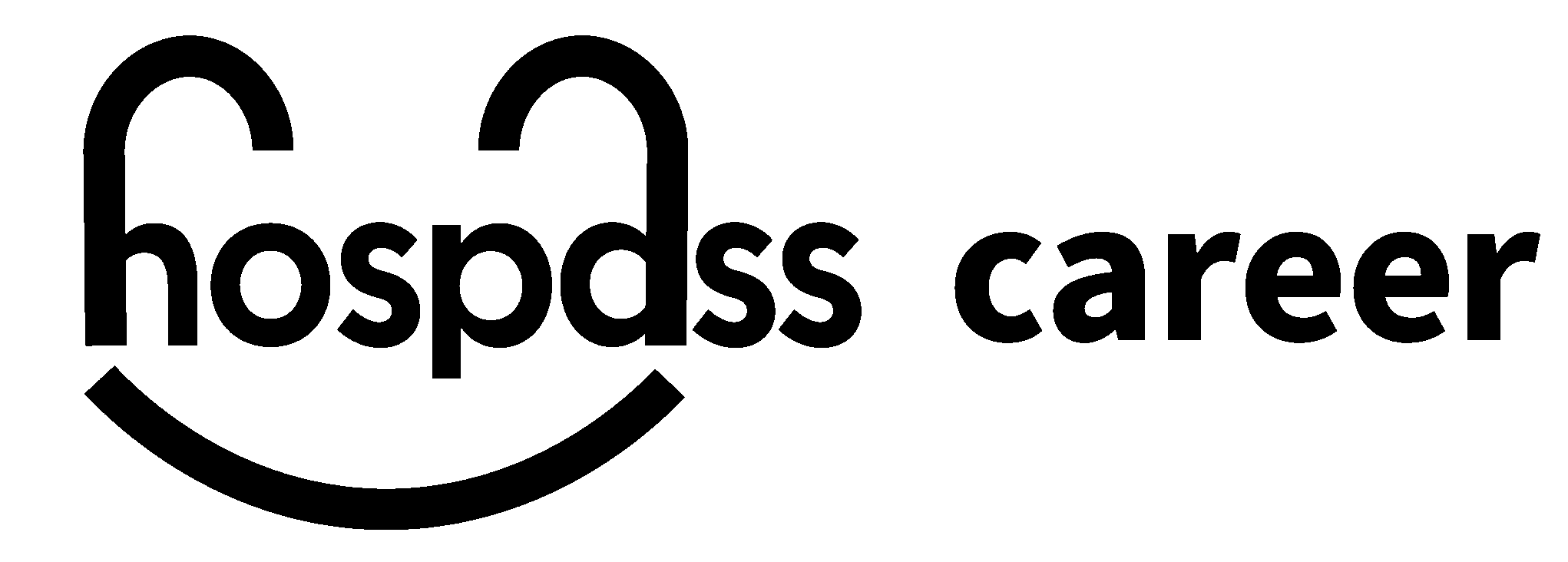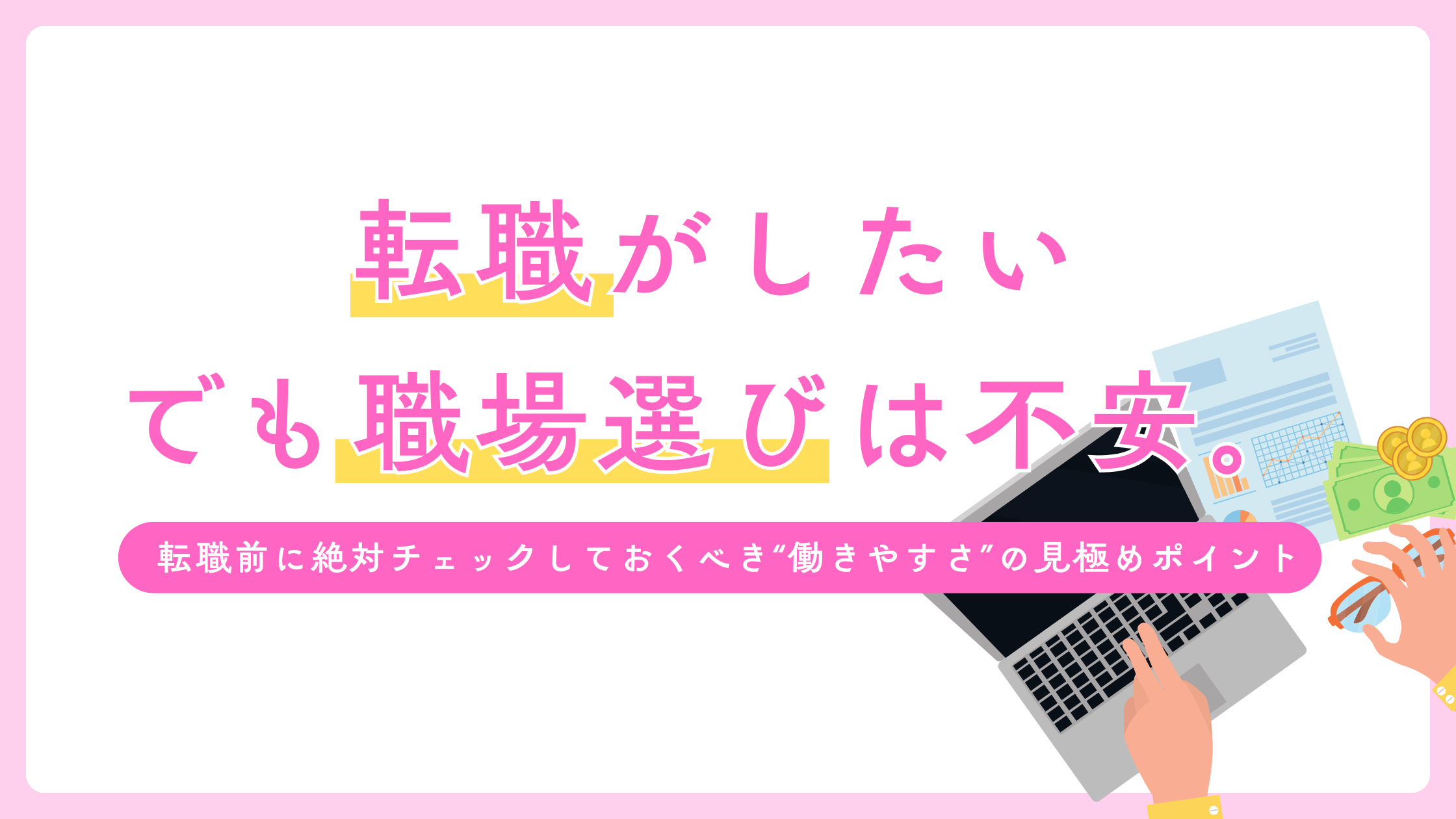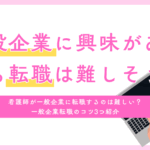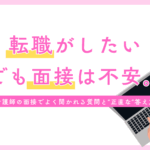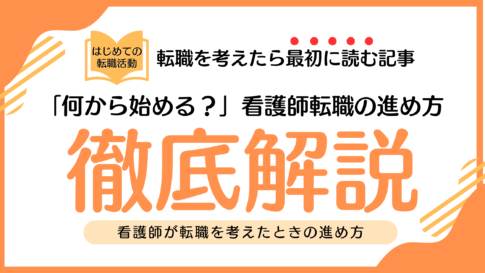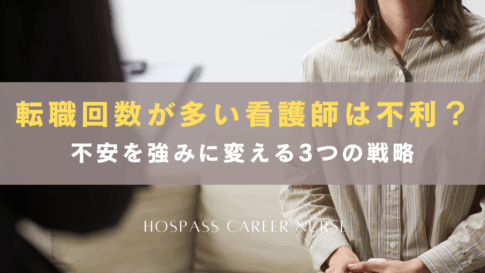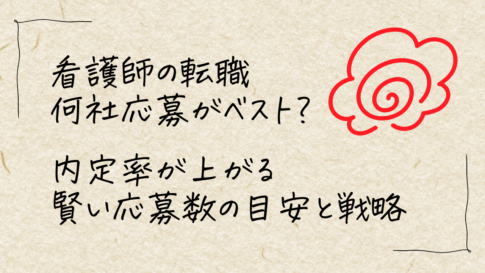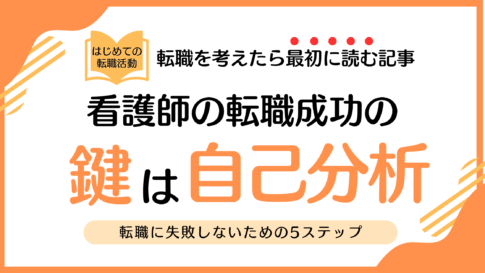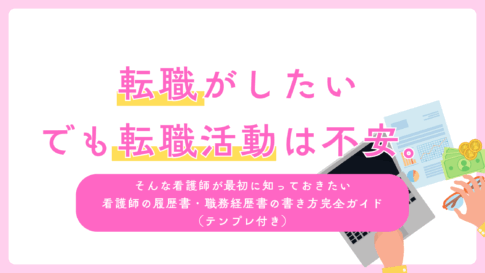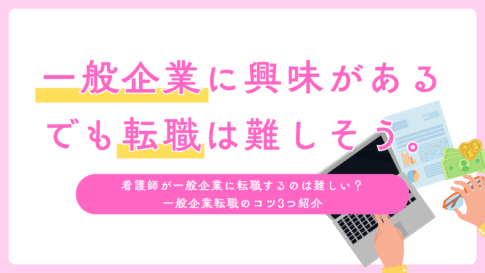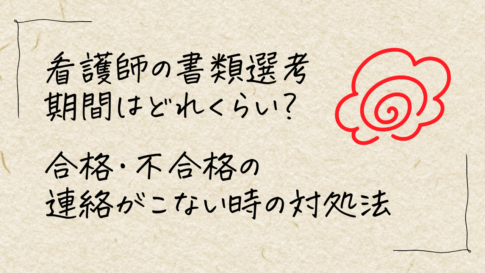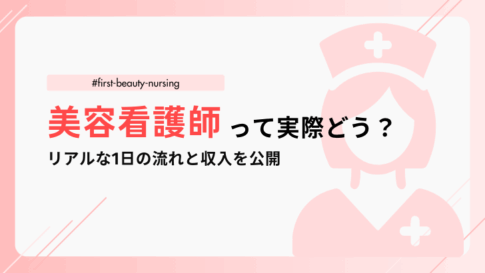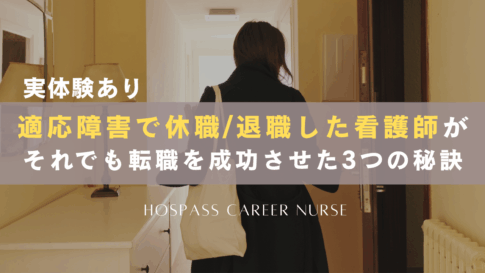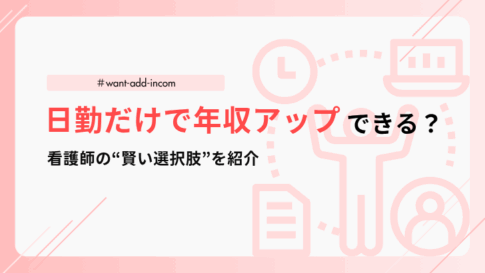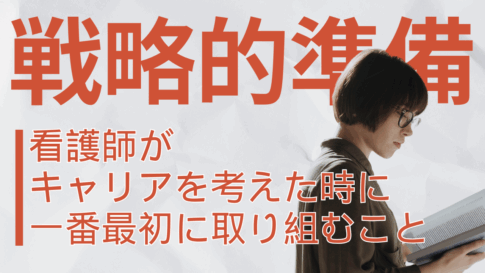転職を考え始めたとき、多くの看護師が気にするのが「次の職場、本当に働きやすいのかな?」という点です。給料や立地はもちろん大事ですが、それ以上に大切なのが「人間関係」や「制度の使いやすさ」といった“見えにくい部分”。
特に初めての転職では、情報収集の方法がわからず、なんとなくの印象で決めてしまいがちです。本記事では、働きやすい職場を見極めるために確認しておきたいポイントを、制度的サポート理論などをもとにわかりやすく解説します。
転職で後悔しないために、ぜひ参考にしてみてください。
制度が“ある”だけでは足りない理由
転職先の福利厚生や制度をチェックする際、多くの人が「産休・育休あり」「時短勤務OK」といった“制度があるかどうか”に目を向けがちです。しかし、実際の働きやすさを左右するのは、「その制度が実際に“使えるかどうか”」という点です。
制度的サポート理論では、「制度の有無」と「制度の使いやすさ」の両方が重要とされています。制度があっても、周囲の目や職場の雰囲気で使いづらければ、実質的に“ない”のと同じになってしまうのです。
制度が使いづらい職場の特徴
- 実際に制度を利用している人がいない
- 利用しようとすると上司に渋い顔をされる
- 「制度はあるけど、人手が足りなくて使えない」と言われる
こうした職場では、制度が「飾り」になっており、安心してライフイベントと向き合うことが難しくなります。
制度が使いやすい職場のチェックポイント
- 産休・育休の取得実績があるか
- 復帰後の働き方に柔軟性があるか(時短勤務や部署異動など)
- 面接時に制度について具体的に説明してくれるか
- 先輩スタッフの制度利用体験が共有されているか
これらは職場見学や面接で確認できることが多いため、ぜひ事前に質問しておきましょう。
制度だけでなく「文化」も大事
制度があっても「遠慮して使わない空気」がある職場では、長く働き続けるのは難しいかもしれません。逆に、制度が整っていなくても、上司が理解を示し柔軟に対応してくれる職場もあります。
制度の整備と職場の文化、両方を見て判断することが大切です。
働きやすさの“見えにくい”ポイントに注目
求人票やホームページだけでは伝わりにくい「働きやすさ」の本質は、実は“空気感”や“文化”にあります。表面的な条件だけでは見抜けない、職場の内側にこそ「長く働けるかどうか」のヒントが隠れています。
1. 人間関係や職場の雰囲気
- 上司と部下の距離感が近いか、風通しが良いか
- 年齢や経験の違いを超えて、お互いを尊重する文化があるか
- ミスを責めるよりも、改善を支える姿勢があるか
これらは、職場見学の際のスタッフの表情や、すれ違うときのあいさつの雰囲気などからも感じ取ることができます。
2. 暗黙のルールがないか
制度があっても、下記のような“暗黙のルール”が働きやすさを損なう要因になります。
- 「子どもが熱でも休みにくい」
- 「育休からの復帰は夜勤免除なしが当たり前」
- 「時短勤務者への無言のプレッシャーがある」
制度があっても、こうした雰囲気があると、安心して制度を利用することができません。
3. 職場の柔軟性
働き方に対する柔軟性がある職場かどうかも見極めポイントです。
- 急な家庭の事情にも配慮がある
- 業務の属人化を避け、誰かが抜けても対応できる体制がある
- 多様な働き方(夜勤専従・日勤常勤など)が受け入れられている
これらは、ライフステージが変わっても働き続けられるかどうかを左右する要素になります。
職場見学・面接で“見抜く”コツ
転職先の「働きやすさ」は、実際にその職場に足を運んだり、面接でのやりとりを通じて垣間見えることも多いです。このセクションでは、職場見学や面接時に確認すべき具体的なポイントを解説します。
1. 見学時にチェックしたい職場の“リアル”
見学は、単なる施設紹介ではなく、“職場の空気”を肌で感じる大切な機会です。以下の点を意識して見てみましょう。
- スタッフの表情は明るいか?
- 多職種との連携はスムーズそうか?
- 話しやすい雰囲気があるか?
- スタッフ間の会話に余裕があるか?
また、休憩室やナースステーションの掲示物にも注目しましょう。情報共有がしっかり行われている職場かどうかも見えてきます。
2. 面接で質問すべき「働きやすさ」関連の項目
面接は、採用されるかどうかを見られる場であると同時に、応募者が職場を見極める機会でもあります。以下のような質問を用意しておくとよいでしょう。
- 「産休・育休を取得された方の実例はありますか?」
- 「時短勤務や夜勤免除など、ライフステージに応じた働き方は可能ですか?」
- 「急な休みや家庭の事情に対するフォロー体制はありますか?」
- 「有給の取得率はどのくらいですか?」
これらは、実際に制度が“使われているか”を確認する重要な問いになります。
3. 面接官の反応から見える“本音”
質問に対する面接官の返答の中にも、職場の価値観がにじみ出ます。
- 回答が曖昧だったり、言い淀んだりする場合は要注意
- 「制度はあるけど…」という枕詞が頻繁に出る職場は、使いにくい可能性あり
- ポジティブな例(具体的なエピソード)がスムーズに出てくる場合は安心材料
【注釈①】:こうした“制度の実用性”に関する見極めは、制度的サポート理論にも通じます。単に制度が「あるか」ではなく、「使いやすさ」が整っていることが働きやすさの鍵となります(参考:『制度的サポートと職場定着』厚生労働省白書 2023年版)
「制度がある職場」と「制度が活きる職場」の違い
福利厚生や両立支援制度が「ある」ことと、実際に「活用されている」ことは大きく異なります。この章では、その違いを明らかにしながら、看護師が本当に働きやすいと感じられる職場の特徴を紐解いていきます。
制度があっても“活用されていない”職場の特徴
制度の有無を就業規則で確認しても、実際に現場で活用されていないケースは少なくありません。以下のような特徴がある職場には注意が必要です。
- 制度についての説明が曖昧で、実例が出てこない
- 「使ったら迷惑をかける」という空気がある
- 制度利用者が“職場にいない”もしくは“非正規”になっている
- 「前例がない」が理由で利用できないことが多い
こうした職場では、表向きは制度が整っているように見えても、実態として利用が難しく、結果的に離職の要因となることもあります。
制度が活きている職場の共通点
一方で、制度が“当たり前に使われている”職場には、以下のようなポジティブな文化が根づいています。
- 育休明けの復帰スタッフが在籍している
- 時短勤務や家庭都合のシフト調整が自然に行われている
- マネジメント層が制度利用をポジティブに捉えている
- ライフイベント後も継続してキャリアを積んでいるスタッフが多い
このような職場は、制度を通じて多様な働き方を受け入れる土壌が整っており、安心して長く働くことができます。
「使いやすさ」は制度運用の“文化”に宿る
制度が“ある”かどうか以上に大切なのは、「文化として受け入れられているか」です。たとえば以下のような職場文化は、働きやすさの指標になります。
- 上司が制度利用に理解があり、相談しやすい
- 「お互いさま」の気持ちで助け合える空気がある
- チーム内に育休・時短勤務経験者がいる
【注釈②】:制度的サポート理論(instrumental support theory)においても、「実際に利用できる制度がある」ことが職場定着や従業員満足度に影響するとされています(出典:厚生労働省『職場の両立支援制度と活用実態』2022)。
「働きやすさ」は自分で確かめる時代へ
求人票やホームページだけでは見えてこない「本当の働きやすさ」。今は情報があふれている時代だからこそ、表面的な情報ではなく、自分にとっての「働きやすさ」を見極める目が求められます。
見学や面接では“空気感”を観察する
職場見学や面接は、求人票ではわからない実情を感じ取る大切な機会です。以下のポイントを意識して観察すると、実際の働きやすさを見極めやすくなります。
- 職員同士の会話や雰囲気に「余裕」があるか
- 時短勤務や子育て中スタッフが自然に働いているか
- 見学時に案内してくれる職員がいきいきしているか
- 「制度の具体的な利用例」について答えてくれるか
施設の設備よりも、「人の表情」や「雰囲気」が何よりの判断材料になります。
チェックリストで“見える化”する
働きやすさは感覚的なものと思われがちですが、下記のようなチェックリストを使うことで、自分に合う職場を“言語化”できます。
- 産休・育休など制度の利用実績があるか
- 時短勤務やシフト融通に柔軟か
- 有給取得率・残業時間の目安はどうか
- キャリア相談や定期面談があるか
- 上司との距離感は適切か
複数の職場を比較する際も、こうした視点があると冷静な判断がしやすくなります。
一人で悩まず、プロに相談するという選択肢も
転職に失敗しないためには、「情報の精度」と「相談できる相手」が鍵です。最近では、LINEやZoomで無料相談ができるキャリア支援サービスも増えています。
- 応募前に職場のリアルを知る
- 第三者視点でのアドバイスを受けられる
- “使える制度”が本当に活きているかの裏取りができる
【注釈③】:制度的サポートの“有無”だけでなく、“運用の実態”を第三者とともに確認することで、より良い意思決定につながることがわかっています(参考:日本労働政策研究・研修機構『職場の制度活用と離職率の関連』2021)。
働きやすさ」は、自分の基準で見極めていい
転職において「働きやすさ」は、年収や勤務地以上に重要な判断基準となることがあります。しかしその実態は、求人票や施設のHPからだけではなかなか見えてこないものです。
この記事では、働きやすさを見極めるための以下のポイントを紹介しました。
- 制度の“使える”と“使いやすい”の違いを理解する
- 職場の雰囲気や空気感を見学や面接でチェックする
- 働きやすさチェックリストで自分の希望を言語化する
- 一人で悩まず、信頼できる第三者に相談することの重要性
「せっかく転職したのに、思っていた職場と違った…」とならないためにも、自分なりの“軸”を持って職場を選ぶことが、後悔しないキャリア選択につながります。
まずは、誰かに話してみることから始めませんか?LINEで気軽にキャリアの相談ができるサービスもご用意しています。
あなたの“納得のいく働き方”を一緒に見つけましょう。